|

|
県道39号にぶつかるT字路になる。
右に行くと国分寺、国分尼寺跡、
左へ行くと、さぬき国府跡。
とりあえず、右に曲がって
国分寺跡を見ることにする。
|
|

|
石碑発見。
石碑には 「史跡 國分尼寺跡」とある。
その跡にしては、あまりに小さな田んぼである。
背景の山をみると、峰が二つ並んでいる。これは、奈良の二上山ではないが、神聖な山のしるしかもしれない。
この碑の向かいに市の生活相談センターのような建物があった、
その建物の道沿いには、
お遍路みちの道の石碑が並べられていた(1,2,3)
この碑はあちこちにあったのを
ここにまとめたものだそうな。
日曜日なのに開いていて、
市の管理担当者のような人がいたので聞いてみると、
この先にお寺があって、
それが国分尼寺だそうだ。
|
|

|
これが国分尼寺だ
|
|
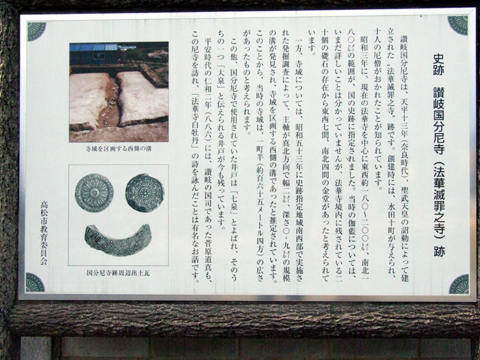
|
お寺の案内板
お寺の境界を示す溝
出土した軒丸瓦
案内板によると、お寺が国分尼寺跡らしい。
「史跡 国分尼寺(法華罪滅之寺)跡」とある。
天平13年聖武天皇の詔勅によって創建されたとある。
讃岐の国司に赴任した菅原道真も仁和2年(886)この寺を訪れ、「法華寺白牡丹」の詩を詠んだとある。
お寺は広かったらしい
発掘調査によって、奈良時代に特徴的な
模様の入った軒丸瓦が出土したそうである。
|
|

|
この国分尼寺に面した道路を挟んで小さな神社があった。これはその堂。
その両側には、陶器製の狛犬がいた。(1雄、2雌)
これは ひょっとして
沖縄の陶器製のシーサーではないか?と思った。
右手(上手)に、ほえているシーサーはオズ。
左手(下手)にいるのがメスだ。
沖縄のシーサーにはそういう決まりがある。
あるいは、名古屋の常滑焼きか?
確かめてみないと分からない。
|
 |
神社の裏、畑の向こうに面白い形をした山。
里山と呼ぶにふさわしい優しさ。
ここが盆栽の生産地であることは知らなかった。
かわいい丸坊主の緑が並んでいた
|


